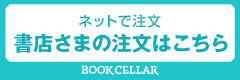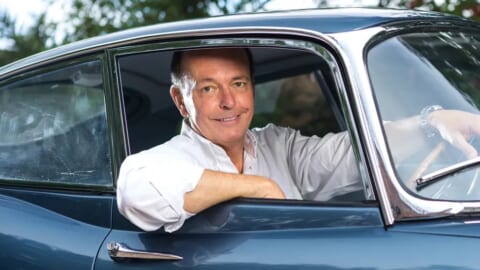内燃機関の集大成Q5と、新世代EVの旗手S6 e-tron。アウディの現在と未来を象徴する2台を徹底比較。その魅力と、デジタル化の先に潜む共通の課題を解き明かす。
アウディ Q5 edition one:デジタル化の光と、動的質感の影
アウディの屋台骨を支えるベストセラーSUV、Q5が第3世代へと進化した。初代から累計270万台以上を販売した成功モデルであり、その新型は日本市場においても極めて重要な存在である。今回試乗したのは、2.0リッターTDIエンジンを搭載する「Q5 edition one」。新開発のPPC(プレミアム・プラットフォーム・コンバッション)をSUVとして初採用し、内外装のデザインからパワートレイン、デジタル技術に至るまで全方位での刷新が図られている。アウディが「スポーティなオールラウンダー」と位置づける新型Q5は、果たしてその期待に応える完成度を見せるのか。英国トップギアの批評的な視点を軸に、その実力を検証する。
デザイン:正常進化の先にある、シャープさと力強さ
新型Q5のエクステリアは、キープコンセプトながらも明らかにモダンでスポーティな印象を強めている。従来よりも高く、幅広になったシングルフレームグリルが力強いフロントマスクを形成し、その両脇にはエアロダイナミクスを意識した機能的なエアカーテンが設けられた。日本のプレゼンテーションでも語られたように、シャープになったLEDヘッドライトや流れるようなボディラインは、先代のイメージを継承しつつも、より洗練された印象を与える。
試乗車は「edition one」のため、スタイリッシュなSportbackボディであり、そのルーフラインは先代よりもさらに流麗になった。トップギア誌が指摘するように、Sportbackはデザインコンシャスでありながら、荷室容量の犠牲はSUVボディ比でごくわずか(515L対520L)に留まっており、実用性を損なっていない点は評価できる。
また、アウディの代名詞であるライティング技術も進化している。オプションのOLEDリアライトはカスタマイズ可能なライトシグネチャーを持ち、オーナーの所有感を満たすだろう。さらに、日本仕様のプレゼンテーションで紹介された、ガラスにハイマウントストップランプを投影する「リアウィンドウプロジェクションライト」は、安全性と先進性を両立するユニークな試みである。
インテリア:支配的なスクリーンと、失われた触感
インテリアは、エクステリア以上に劇的な変化を遂げた。トップギア誌が「スクリーン、スクリーン、そしてさらにスクリーン」と表現したように、物理スイッチを極限まで排した「デジタルステージ」が乗員を迎える。運転席の正面には11.9インチのバーチャルコックピット、そして中央にはドライバー側に傾けられた巨大な14.5インチのMMIタッチディスプレイが鎮座する。これに最上位グレードでは助手席側の10.9インチスクリーンも加わる。プレゼンテーションでは、これを「ヒューマンセントリック(人中心)」なデザインと説明したが、その実態はデジタルデバイスへの完全な移行である。
ディスプレイの応答性は高く、グラフィックも鮮明だ。しかし、トップギアのレビューアーが嘆くように、空調操作までタッチスクリーンに統合されたのは、直感的な操作性を犠牲にしたと言わざるを得ない。さらに問題なのは、ステアリングホイールだ。四角い形状もさることながら、そこに配置されたタッチセンサー式のハプティックボタンは、意図しない操作を誘発しやすく、運転中のストレス要因となりかねない。確実な操作感が求められる部分に、なぜこのインターフェースを採用したのか、疑問が残る。
素材の質感については、高級ドイツ車としての水準は保っているものの、一部に安価なプラスチックが見受けられ、シルバートリムが本物の金属ではないなど、トップギアが指摘する「素材の選択ミス」も散見された。デジタル化の波は、時にアウディが長年培ってきたはずの、触感を通じた品質の高さを置き去りにしてしまったようだ。
パワートレインと走行性能:MHEV Plusの恩恵と、拭えない雑味
試乗したTDIモデルは、204psと400Nmを発生する2.0リッター4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載する。新型Q5のパワートレインにおける最大の進化は、全モデルに搭載された「MHEV Plus」と呼ばれる48Vマイルドハイブリッドシステムである。[3] これは従来のスタータージェネレーターに加え、ギアボックス後部に18kW/230Nmを発生するモーター(PTG)と、1.7kWhの水冷式バッテリーを組み合わせたものだ。
このシステムの恩恵は大きい。日本のプレゼンテーションで強調されたように、低速域ではエンジンを完全に停止させ、モーターのみでの独立した走行が可能である。発進は常にモーターが担うため、ディーゼルエンジンが苦手とする出足のレスポンスは劇的に改善された。ガソリンから電気への切り替えも非常にスムーズで、日常域での洗練度は高い。
しかし、トップギアが指摘するように、ひとたびアクセルを踏み込むと、ディーゼル特有のうなり音がキャビンに侵入してくる。高速巡航に入れば落ち着きを取り戻すが、低中速域でのノイズはプレミアムSUVとして物足りなさが残る。7速デュアルクラッチトランスミッションも、効率を重視するあまり、時に反応の鈍さを見せることがあった。
乗り心地とハンドリング:期待を裏切る硬さと、最大の欠点
新型Q5の動的質感において、最も厳しい評価を下したくなるのが乗り心地と静粛性である。試乗車はオプションのアダプティブエアサスペンションを装備していたが、その乗り心地は驚くほど硬質だった。路面の大きな凹凸は、吸収しきれずに乗員に直接的な衝撃を伝えてくる。硬いサスペンションのおかげでコーナーでのロールは少ないが、「コンフォート」の名を冠するモードに期待するしなやかさには程遠い。
そして、最大の欠点はロードノイズの大きさだ。かなり拾ってしまう。20インチホイールを履いていたとはいえ、これは看過できない問題である。路面からの騒音が絶えずキャビンに侵入し、長距離走行では疲労の原因となるだろう。
一方で、新プラットフォームの恩恵はステアリングフィールに現れている。プログレッシブステアリングは低速では軽く、速度を上げると適度な手応えを示し、車両のコントロールは容易だ。しかし、ブレーキ・バイ・ワイヤーを採用したブレーキペダルは、回生ブレーキとの協調制御が影響しているのか、フィールが硬質で、スムーズな減速には慣れを要した。
総括:先進性の代償
第3世代となったアウディQ5は、大胆なデジタル化と進化したハイブリッドシステムという明確な武器を手に入れた。しかし、その一方でプレミアムSUVに求められる最も基本的な価値、すなわち快適な乗り心地と静粛性という点において、深刻な課題を抱えている。
特に、圧倒的なロードノイズは「スポーティなオールラウンダー」というよりも、洗練性を欠いた乗り物という印象を与えかねない。先進的なデジタルステージも、使い勝手の面では退化している部分がある。ベストセラーのフルモデルチェンジという難しいタスクにおいて、アウディは革新を追求するあまり、熟成という道を忘れ、動的質感という大切な要素をどこかに置き忘れてしまったかのようだ。これが、新型Q5に対する率直な印象である。
アウディ S6 Sportback e-tron:電動化時代の美しきアスリート
アウディがポルシェと共同開発した新世代の電動プラットフォーム「PPE(プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック)」を纏う第2弾モデル、A6 e-tron。そのハイパフォーマンス版である「S6 Sportback e-tron」は、内燃機関の時代に名を馳せた「S」の名を受け継ぎ、電動化時代のアウディのスポーツセダン像を提示する一台である。英国トップギアがベースモデルのA6 e-tronを「ハンサムなサルーン」と評した流麗なデザインに、最高出力543bhpを誇るツインモーターを搭載。果たしてこの美しきアスリートは、伝統と革新をどのように融合させているのか。その真価に迫る。
デザイン:空力がもたらした、機能的な美しさ
S6 e-tronのエクステリアは、理詰めと感性が高度に融合した、まさに機能美の結晶である。奇をてらうことなく、正統派のサルーンとしての美しさを湛えている。SportbackボディのCd値は、驚異的な0.21を達成。これは、フラッシュサーフェス化されたグリル、アクティブシャッター、フラッシュドアハンドル、そして床下をフラットにするなど、綿密な空力計算の賜物である。
フロントのブラックマスクは、ヘッドライトやセンサー類を巧みに隠し、クリーンな表情を生み出す。日本のプレゼンテーションで紹介された、サイドのドアパネルと窓の比率を3対1にする手法は、バッテリー搭載による腰高感を視覚的に抑え、コンセプトカーさながらの伸びやかなプロポーションを実現している。
さらに、8種類から選択可能なデイタイムランニングライトのシグネチャーや、オプションで点灯するアウディのフォーリングスエンブレムは、デジタル時代の新しい表現方法であり、所有する喜びを高めるだろう。このクルマがSUVではない、という一点だけでも、高く評価する価値がある。
インテリア:デジタルステージの洗練と、残された課題
インテリアの基本的な構成は、Q5と同じく「デジタルステージ」である。11.9インチのバーチャルコックピット、14.5インチのセンターディスプレイ、そしてオプションの10.9インチパッセンジャーディスプレイが並ぶ。しかし、A6 e-tronでは、そのレイアウトがより洗練され、トップギアが評するように「威圧的ではない」空間に仕上がっている。
ダッシュボードに布地を張るなど、ソフトタッチ素材が効果的に使われており、キャビンの雰囲気は上質だ。シートの座り心地も快適で、フロア下にバッテリーを搭載しているにもかかわらず、不自然な着座姿勢を強いられることはない。センターコンソールに物理的なボリュームノブを残した判断は賢明であり、高く評価したい。
しかし、Q5と共通の課題も残る。ステアリングホイールの静電容量式ボタンは、やはり直感的な操作性に欠け、使いにくさを感じる。そして、オプションのバーチャルエクステリアミラー(デジタルドアミラー)だ。プレゼンテーションでは、ユーザーの声を受けてモニター位置を上げるなど、第2世代への進化がアピールされた。だが、「視点を再集中させるのに時間がかかり、使いにくい」という意見が出るのはもっともであり、伝統的なミラーを選択する方が賢明だろう。
パワートレインとパフォーマンス:静寂の中から現れる、圧倒的な暴力
S6 e-tronの心臓部は、フロントとリアにモーターを搭載する電動クワトロシステムである。システム最高出力は543bhpに達し、0-100km/h加速はわずか3.9秒という、スーパースポーツに匹敵する性能を誇る。アクセルペダルを踏み込んだ瞬間から、トルクが即座に立ち上がり、音もなく、しかし暴力的に巨体を押し出す感覚は、高性能EVならではの体験だ。
PPEプラットフォームが採用する800Vアーキテクチャーは、最大270kWの急速充電に対応し、バッテリー残量10%から80%までをわずか21分で完了させる。94.9kWh(使用可能容量)の大容量バッテリーは、パフォーマンスと長大な航続距離の両立に貢献しており、レンジプラスパッケージ装着車で800kmを超える走行が可能とされた。
走行特性と乗り心地:ダイナミズムと洗練性の両立、しかし…
ベースモデルのA6 e-tronは「滑らかで、洗練されており、アウディにしては驚くほどダイナミック」と評価が高い。S6では、そのダイナミズムがさらに研ぎ澄まされている。後輪駆動を主体とするクワトロシステムは、コーナー進入でノーズを鋭く内側に向け、巨体を軽々と旋回させる。シャシーの追従性は高く、ドライバーに自信を与える。
ステアリングは軽く、路面からのフィードバックは希薄だが、その正確性は高い。S6に標準装備されるアダプティブエアサスペンションは、大きなうねりでは極上の乗り心地を提供する一方で、鋭い突起、例えば路面の穴などからの衝撃はキャビンに突き上げてくる二面性を持つ。
ブレーキは、回生ブレーキと物理ブレーキの協調制御が見事で、ペダルフィールは自然だ。ステアリングのパドルで回生レベルを調整できるほか、日本のプレゼンテーションで紹介された、レーダーで前走車を検知して自動で回生ブレーキをかける機能は、賢く、実用的である。
しかし、この美しきアスリートにも弱点はある。Q5と同様、ロードノイズの問題だ。トップギアは、特定の路面状況下で耳障りな共振音が発生することを指摘している。完璧な静粛性を持つパワートレインだけに、ロードノイズや風切り音が際立ってしまうのかもしれない。
総括:電動スポーツセダンの新たな指標
アウディ S6 Sportback e-tronは、電動化がもたらすパフォーマンスの新たな可能性と、アウディが長年培ってきたデザイン、そして品質を見事に融合させた一台である。息をのむほど美しいスタイリング、内燃機関のSモデルを凌駕する圧倒的な加速性能、そして長大な航続距離は、間違いなくこのクルマをセグメントの新たなベンチマークへと押し上げるだろう。
もちろん、静電容量式ボタンやバーチャルミラーといった操作系、そしてロードノイズという課題は残されている。しかし、それらを差し引いても、S6 e-tronが放つ魅力は色褪せない。これは単なる速いEVではなく、アウディというブランドが電動化の未来に向けて提示した、明確かつ説得力のある回答である。重厚なエンジンサウンドは失われたが、その代わりに手に入れた静寂と暴力的なまでのパフォーマンスは、新しい時代のスポーツセダンの価値観を我々に問いかけている。
まとめ:過渡期のアウディが示す、二つの未来像
今回試乗したアウディQ5とS6 e-tronは、内燃機関から電気自動車へと移行する、まさに現代のアウディを象徴する2台であった。
Q5は、ベストセラーモデルの進化形として、内燃機関の効率と洗練を「MHEV Plus」で極めようとした意欲作である。しかしその結果は、快適性や静粛性といった自動車の根源的な価値において課題を残すものとなった。大胆なデジタル化は、時にドライバーとの直感的な対話を妨げる結果にもなっている。これは、内燃機関の最終章におけるアウディの迷いを映し出しているのかもしれない。
一方、S6 e-tronは、PPEという白紙のキャンバスに、アウディが思い描く電動化時代の理想像を描き出したモデルだ。デザイン、パフォーマンス、効率性のすべてにおいて、内燃機関の呪縛から解き放たれた自由な発想が見て取れる。それは極めて魅力的で、未来への期待を抱かせるものだ。しかし、こちらも操作系やロードノイズという、Q5と共通する課題を抱えている。
この2台から見えてくるのは、アウディが現在、壮大な技術的変革の渦中にあるということだ。両車が共通して採用する「デジタルステージ」というコンセプトと、それに伴う動的質感の課題は、アウディが全社的に取り組むべきテーマであることを示唆している。内燃機関の集大成と、電動化の新たな始まり。どちらも完璧ではないが、それぞれがアウディの現在地と未来への意志を力強く示している。この過渡期の先で、アウディがどのような答えを見つけ出すのか、その進化から目が離せない。
400号記念:UK400マイルロードトリップ/フェラーリ F80/フェラーリハイパーカー:トップギア・ジャパン 069
このクルマが気になった方へ
中古車相場をチェックする ![]()
ガリバーの中古車探しのエージェント
![]()
今の愛車の買取価格を調べる カーセンサーで最大30社から一括査定
![]()
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大10社に無料一括査定依頼
![]()
新車にリースで乗る 【KINTO】
安心、おトクなマイカーリース「マイカー賃貸カルモ」
年間保険料を見積もる 自動車保険一括見積もり